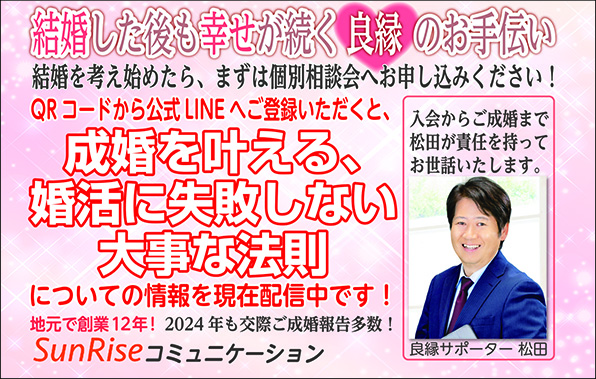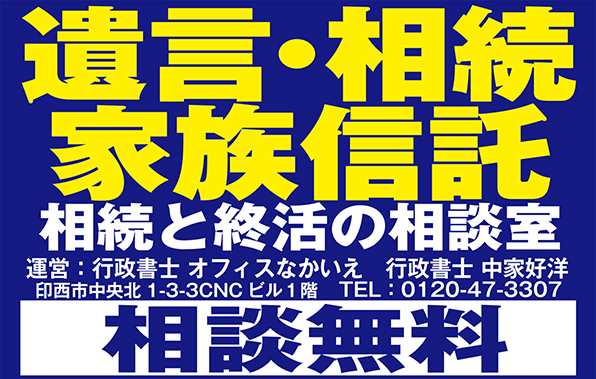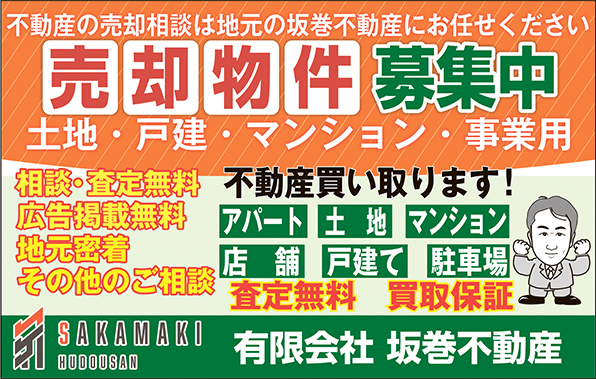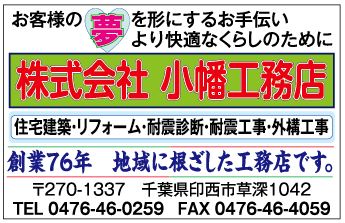2025/08/12_いんざいの生きもの紹介
- sekisei
- 2025/08/12
第十五回「サワガニ」
斜面林下のみよ(台地に降った雨水が湧き出ている水路)や田んぼでは、サワガニをよく見かけます。サワガニのことを「清水ガニ」と呼んでいると地元の人から聞いたことがあります。畑を耕している時に出てくるサワガニは、そこに水があることを教えてくれるのだそうです。

サワガニは、淡水のカニの仲間としては、他のカニとは違う全く特殊なカニです。普通の淡水のカニは、普段は、陸地の水辺にいますが、産卵するのは、海の浜辺なのです。有名なのは、オーストラリアのクリスマス島に生息するアカガニです。抱卵したメスが道路を真っ赤に染めて海に向かう姿を映像でご覧になった方もいるでしょう。(ちなみに、道路を一次通行止めにしたり、カニの通り道を作ったりして、保護している場所もあるようです)日本でもこのような光景は見られます。

海で産卵するカニは、たくさんの卵を持っていますが、一生を陸ですごすサワガニは、せいぜい50個くらいの卵を産み、それをお腹に抱えて、稚ガニになってもしばらくは母カニが大切に育てます。

印西に見られる淡水のカニに、モクズガニがいます。海で産卵します。上海ガニの仲間で、とてもおいしいので、房総半島では名物です。このモクズガニを、ニュータウン地区に降る雨をためる調節池で、2017年に見たことがあります。

もとは田んぼだった谷津を2か所、土手でふさいで作った池でした。産卵のために海に帰らなければならないはずですが、土手にはばまれ、道路にはばまれ、川へは簡単には近づけません。そこで一生を終えるのかと、池に放しましたが、聞くところによると、どんなに困難があっても、丘を越え、野を超えて海に向かおうとするのだそうです。無事に子孫を残していますように。

添付写真 5枚 提供 いずれも亀成川を愛する会
- サワガニ
- サワガニ
- サワガニ 別所緑地
- サワガニ 別所
- モズクガニ 地面に
いんざいの生きもの紹介
NPO法人 亀成川を愛する会 理事長
森林インストラクター
小山尚子