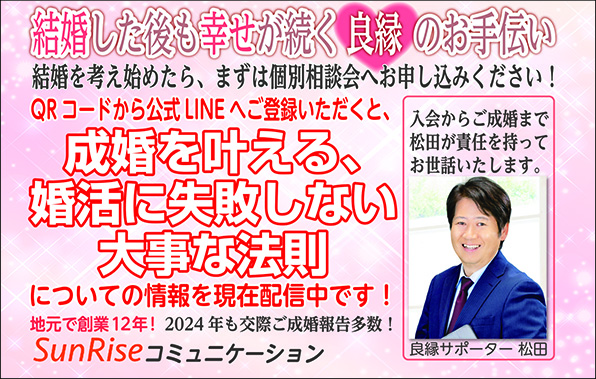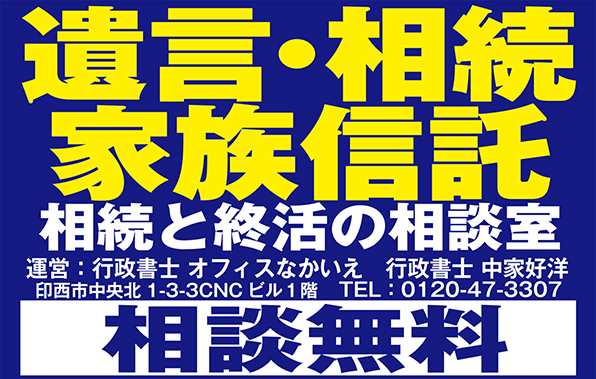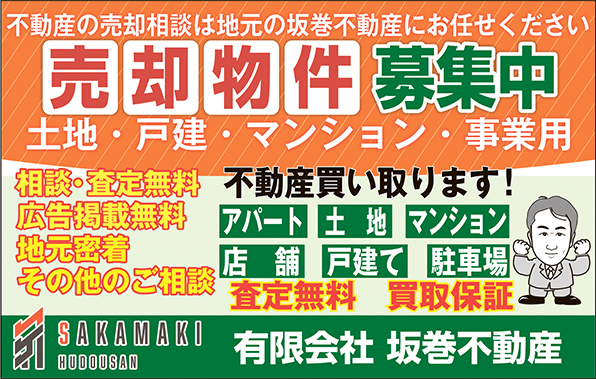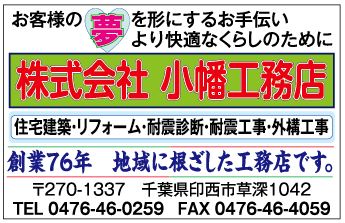2025/06/16_特集 今、データセンターを考える
- sekisei
- 2025/06/16
DX((デジタルトランスフォーメンション)や生成AIの普及によって、データセンターの需要が加速度的に拡大している一方、印西市や白井市の住宅隣接地域では、新たなデータセンター建設計画を巡って、住民の反対運動が相次いでいる。
この問題の根元には、全国各地で起きている太陽光発電を目的として設置されたソーラーパネルによる住環境トラブルや森林の大規模伐採による自然環境破壊と同様、新しい技術や開発事業者の現状、スピードに法の規制が全く追いついていない、新しい規制が急務なのにその動きが鈍い国の対応に一番の問題があるのではないか?
例えば、データセンターは建築基準法上の用途として、「事務所」もしくは「倉庫」として扱われているが、データセンターという建物を全く想定していなかった時代の「事務所」や「倉庫」をデータセンターに適用すること自体に無理があるように思える。
本号では、
- 4月に突然発表されたデータセンター建設計画に対する近隣住民の懸念、反対運動(印西市)の事例
- 新たに2つの地区で建設が計画されている白井市、そしてその計画の進捗状況と問題点や課題(白井市市議会議員 柴田圭子氏 ご寄稿)
- 自社サービス需要拡大に対応、「白井データセンターキャンパス」3期棟増設(株式会社インターネットイニシアティブ IIJ )
についてお伝えする。
【印西市】
突如、判明したデータセンター建設計画
4月3日、千葉ニュータウン中央駅北口から徒歩5分の敷地内(約1万平方メートル)に「データセンターを建設する」旨の開発事業公開板(標識板)が掲示された。公開板によれば、このデータセンターは地上6階、塔屋1階、延床面積 約30,500平方メートル、高さ52.7mで東側に隣接するマンション(15階建て、高さ約45m)を上回る。窓もない箱のような無機質な異様な高さの建物が建設されることになる。
事業者は令和8年1月19日に工事を開始、2年後の令和10年2月末完成を目指している。

データセンター建設予定地 左 隣接されるマンション( 15回建て、中央奥方向に千葉ニュータウン中央駅は、写真中央奥方向、右 商業施設階段入口

近隣住民の懸念
特に以下のような点が指摘されている。
- 交通事故リスク サーバーの搬入(新規)及び、数年後の入替のため大型10トントラックが、サーバーラックを大量に搬入、搬出。ラックの数は、数百〜数千と想定される。子供たちの通学路への出入り事故が心配。(命に関わる問題) 小倉台小学校には、全校生徒1100名が通っています。
- 騒音リスク 24時間365日稼働音が発生。地下重油タンクの試運転も、大きな騒音が懸念(事業者にしっかり説明を求めたいポイントの1つ)。
- 屋上からの排熱リスク 南風が吹くので、高層階を直撃。気温35度の日に、45度の熱風になるとの試算もある。
- ・スマホの電波障害 電波がつながりにくくなる可能性。生活に影響。
「タウンセンター地区の活用を考える会」を設立、
目的は、計画を強行してもメリットよりデメリットが大きいことを業者認識させ、建設計画を断念させること。
4月に設立し以降毎月1回以上、集会を開催している。会員は月を追うごとに増えている。具体的には、以下のようなことを進めてきている。

事業者側との折衝
印西市、千葉県、国会議員、県会議員、市会議員への働きかけ
メディアへの情報発信、
近隣自治会との連携、情報共有
地区計画の検討
デジタルを含む建設反対の署名活動の準備
【白井市】
白井市内で計画されている2つのデータセンターの状況
白井市 市議会議員 柴田圭子
白井市内においてもデータセンター建設が複数箇所予定されたり、すでに着工されたりしているところがあります。
その中で2か所、建設予定地近隣に住む住民から、疑問の声が上がっているところがあります。
ひとつは、ニュータウン区域である白井高校や南山3丁目・池の上1丁目に隣接する富ヶ谷という市街化調整区域(主に梨畑)に計画されているデータセンター(以下「富ヶ谷地区DC」)。本来建物の建たない調整区域に、地区計画を作ることで建築を可能とする都市計画法の特例を適用し、計画が進んできました。
もう一つは、千葉ニュータウン中央駅圏にある桜台で計画されているデータセンター(以下「桜台地区DC」)。ここは社会保険大学校跡地。近隣商業地域で地区計画もあるところです。注目を集めている印西市のイオンモール駐車場跡地に計画されたデータセンターから西に800mほど進んだところに位置します。
<富ヶ谷地区DC>
周辺が戸建て住宅と小中学校等の文教施設がある市街化区域に隣接した、本来開発が抑制される調整区域(約13万㎡)に高さ40m(マンション13階相当)のデータセンターが4棟建設される計画です。都市計画法上の手続きと白井市まちづくり条例に基づく手続きの二つが並行して進んでいます。
都市計画法の特例を使って、事業者と地権者が地区計画の案を作り提出。市は近くにインターができることもあり、この辺りは事業誘致の候補地として選定しており、データセンター誘致で進めることにGOサインを出しています。
そもそもは、後継者不足等で梨の耕作継続が困難になっている土地も含んだ地域でした。地権者がただ耕作放棄地にするのではなく、市にとってプラスになるような土地利用を工夫しようということで話し合い、サウンディング調査も行って、近隣の住宅街への配慮もしたうえで決定したのがデータセンターです。近隣との話し合いの中で、建物の棟数を減らす、圧迫感を軽減するよう階段状の建物にするなど複数回修正も出されてはいるのですが、示された地区計画自体、調整区域という建設抑制されるべきところに、駅前並みの高さ40mの建物を許容するもので、場所によっては大幅に日影がかかるところもあり、近隣からはまだ理解は得られていません。
まちづくり条例に基づき、4月に開発事業事前協議書の縦覧があり、近隣住民から300通を超える意見書が寄せられています。意見書に対しては市及び事業者が回答書を作成することになっており、相当時間がかかると思われます。
また地区計画自体は、4月に地区計画原案の縦覧と地権者等からの意見書提出、5月には市民や利害関係者を対象とした縦覧と意見書の提出があり、こちらにも300通を超える意見書が寄せられています。
地区計画の方は、白井市都市計画審議会が開かれ、最終決定がされます。
<桜台地区DC>
桜台地区DC予定地は、3.6万㎡。ニュータウン区域内で、464号にも面しています。北側は片側1車線の市道をはさんでマンションが、西側は戸建て住宅地です。この土地は用途が近隣商業地域で地区計画も定まっています。しかし、地区計画に定められた敷地境界からのセットバック(壁面後退)が、464号側が10mなのに対し、戸建て住宅との境はわずか2メートル。つまり、2m離隔を取れば建物の建設が可能となっていて、配慮に欠けており、地区計画自体に不備な点があると言えます。また、社会保険大学校はそんなに高い建物ではありませんでしたし、住宅側からはずっと離れて建てられていたので、日影がかかることもありませんでした。しかし計画されている建物は、高さが向かいのマンションより高く、地区計画に定められた壁面後退値以上に離隔は取られてはいても、日影が大幅にかかります。
さらに、サーバーやラックを搬入する10tトラック(長さ12mにもなる)の入り口を、通学路ともなっている片側1車線の住宅街側に設けようとしており、近隣住民からすれば、安全対策に大いに問題のある計画です。
まちづくり条例に基づく意見書は昨年夏に277通も出され、半年以上かけて3月にようやく市と事業者からの回答がありました。
条例上はこの後、事業者と市が事前協議書を締結すれば手続きは完了となりますが、意見書の回答に対し、住民は納得しておらず、今も協議が続いています。
<まちづくり条例の限界>
白井市は千葉県で初めてまちづくり条例という一定規模以上の開発の際の手続きを定めた条例を制定しています。住民紛争に際し調整機能を持たせるという目的もあり、この条例に則って、近隣住民は建設計画に意見書を提出することができます。
前述した通り、市及び事業者は、それぞれの意見書に回答せねばなりません。しかし、その回答に対してさらに住民が意見を述べたくても、条文上に規定がなく、意見を述べる場は確保されていません。
すべて調整しきれるものでもなく、このように揉めている場合の解決の道筋がみえなくなります。
いずれのケースも、折り合える点が見つけられるのか、対立したまま強行されるのか、市としてどう関与するのか、あるいは関与できるのか、先はまだ見えていません。
<データセンターに付随する問題点>
データセンター建設という問題に直面し、色々な角度から市民が調査し、以下のような点が問題として集約されてきています。
1.建築基準法上の分類がどれにも該当しない
建築物の主要用途一覧にデータセンターの掲載がなく、事務所なのか倉庫なのか、あるいは「その他」に分類されるのかが不明。だが、白井市では事務所と解釈(そうしないと地区計画上立てられないことになる)。
- しかし、事務所と分類すると無理が生じる。
@事務スペースが極度に小さく人も少ない。(桜台DCにおいては建物のわず
か5%)
@365日稼働するため、停電時対策で発電機が必ず設置され、燃料(重油や
灯油)が相当量地下に埋設されている。一般事務所では大量の重油の保管
は認められないので矛盾する。
- サーバーを冷却するために空調が稼働し、外部に排熱し続ける。それも40℃をこえる熱が24時間365日。風向きによっては住宅街に流れる。
- 大量の電力消費とCO2の排出は市の宣言するゼロカーボンシティに逆行する。
- サーバーラック搬入や入れ替え時に10t車が出入りする。通常サーバーはおおよそ一機1tで、数千搬入される。10tトラックだと一台で10のサーバーしか運べず、搬入トラック数は相当なものとなり、住宅地区では、交通上の安全が保てない。
データセンターというのは新しい概念で、今までの分類に入りきらない未知の部分の多い建物です。賑わいをもたらすものではなく、無機質な大きな建物です。しかも排熱し、電力消費も著しいとなったら、隣接して住宅が広がる土地における開発には、相当な配慮が求められます。
至急国が位置づけを明確にし、規制すべきは規制するという対応が求められていると考えます
【白井市】
IIJ 株式会社インターネットイニシアティブ 「白井データセンターキャンパス」3期棟増設
IIJは、白井市で運用しているデータセンター「白井データセンターキャンパス」(以下、白井DCC)において、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や、 AI活用の進展に伴う、クラウドセキュリティ、IoT、MVNO等の需要が急速に拡大していることに対応する為、新たに3期棟を増設する。
本年6月1日着工、2026年度中の運用開始を予定。
白井DCCは2019年5月に1期棟の稼働を開始、2023年7月には、クラウド・データセンター事業者、コンテンツ事業者などの旺盛なコロケーション需要などに対応するため2期棟の運用を開始したが、2026年中に2期棟が満床になる見込みで、これをうけて今回、設備増強を主な目的とした3期棟の増設となった。
3期棟は、エリア敷地面積約5400㎡、受容電量10MW(25MW迄拡張可能)、1000ラック規模で、1期棟、2期棟と同様、直接外気冷却方式を採用するが、今後、AI用途のGPU搭載サーバ等発熱量が著しく高いIT機器の収容を視野に、水冷設備に必要な専用熱源のスペースや冷水配管ルートをあらかじめ確保した「水冷Ready設計」を採用する予定。
3期棟イメージ

白井DCC3期棟の特徴
AI用途のGPU搭載サーバなど発熱量が著しく高いIT機器の利用を見据え、DLC(Direct Liquid Cooling)に代表される水冷方式に必要な専用熱源の設置スペース、熱源からサーバ室内までの冷水配管ルートを確保するなど、水冷Ready設計を採用している。また、冷水機器を実装したサーバラックは従来よりも大型で、給電のための空間もより多く必要であること、さらに空冷能力の増強も必要とされることから、状況に応じてラックの立架位置とサーバ室内の天井開口位置を柔軟に変更ができる「フレキシブル天井」を採用、また、3期棟内に設けられるサーバ室や電気室は、構造的に求められる荷重や階高が異なるが、エリアをゾーニングした上で、ゾーンごとに適した構造計画を適用させるハイブリッド構造を採用、加えて、超高効率AI計算基盤の研究開発で得られた技術を、積極的に活用していくという。
千葉ニュータウンNEWS6月号より