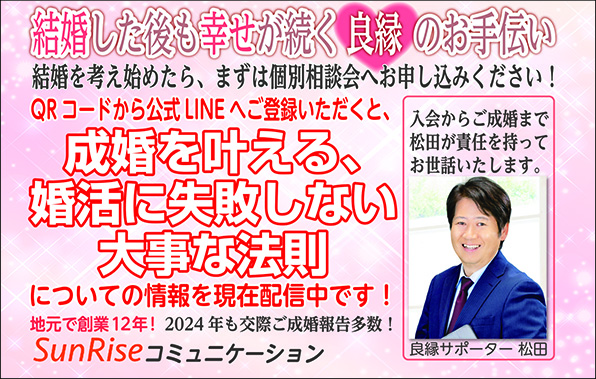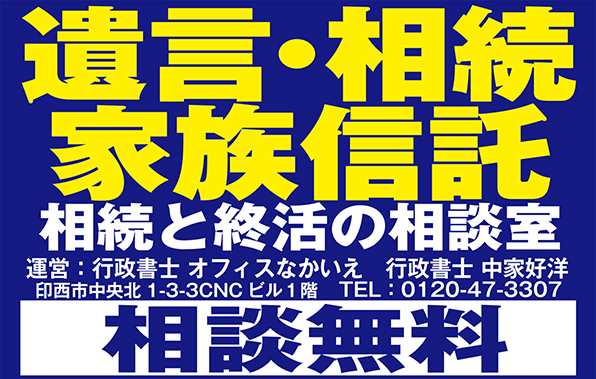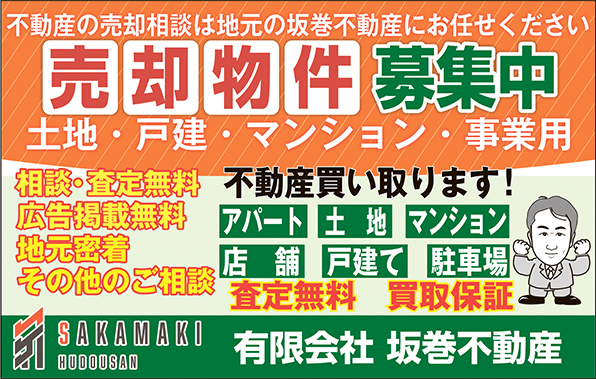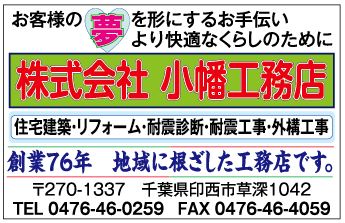2025/10/12_いんざいの生きもの紹介
- sekisei
- 2025/10/12
第十七回 海を渡るチョウ 「アサギマダラ」
今月は、旅するチョウとして知られるアサギマダラの紹介です。虫が苦手な方に昆虫の美しさを語るのは申し訳ないのですが、アサギマダラは、浅葱色の美しい模様を持つ、ひらりひらりと優雅に舞う大型のチョウですから、どうか、最後まで読んでくださいね。
浅葱色といえば、日本古来の多彩な色の名称の中でも、響きも美しい言葉だと思います。新選組の羽織の色ともいわれています。この浅葱色をまとったチョウは、今年も大ヒットしたアニメ「鬼滅の刃」で、蝶屋敷の場面に出演しているチョウではないかと思います。映画を見た時、思わず、「アサギマダラだ!!!!」と心のうちで叫んでいました。
アサギマダラは、春、南から日本列島を北上して、秋には南下します。寿命はチョウとしては長く、5か月くらいですが、さすがに往復するほどの寿命はなくて、途中で産卵し、羽化した個体が秋になると南へ旅します。この旅は九州や台湾にまで及ぶので、海を渡ることになるのです。海を渡る鳥でさえ、あの嵐をどうやって乗り越えるのか不思議ですが、チョウとなると、本当にどうしてそんなことができるのか、生命の不思議と驚異です。

旅の途中、キジョランやイケマなど(山の中や湿った林縁に見られるキョウチクトウ科の植物。イケマはツル性植物で、林縁がアスファルト道路になり、斜面林が管理されなくなって、印西では見ることが少なくなりました)に卵を産みます。これらの植物はアルカロイドという毒素を持っているので、毒を食べて育つアサギマダラは、警戒色の美しい羽を持ち、捕食者から狙われにくくなります。
また、アサギマダラと言えば、秋の七草のひとつ、印西ではもう見られなくなったフジバカマにやってくるのが有名です。フジバカマの蜜にもアルカロイドの一種が含まれており、雄は交尾のためのフェロモンを作るため、この毒素が必要なのだそうです。

印西でこのチョウを見たのは、実は数回しかありません。そのうちの一回は、旅の途中でいったいどうやって見つけたのか、湿地に咲いているサワヒヨドリ(フジバカマと同じ仲間)にいました。写真がうまく撮れなかったため、今回掲載する写真は、弟のフジバカマ畑にやってきたものです。

ところで、同じくらいの大きさでまだら模様もよく似たチョウにアカボシゴマダラがいます。こちらは、悲しいことに、特定外来生物です。幼虫の食草のエノキが国蝶のオオムラサキなどと競合すること、繁殖力がたいへん強いことなどから、在来種への影響が心配です。近年、印西でもたいへんよく見かけるようになりました。